ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ主演、2015年公開の映画『マイ・インターン』に登場する英語を、複数回に分けてまるっと解説します!今回は第2回です!
作品のあらすじ、および第1回はこちらをご覧ください。
- 作品に登場する英語を解説!
- 3分~6分に登場する英語
- I thought that was you. (3分8秒)
- organizational skills (3分21秒)
- a roll-up-your-sleeves attitude (3分26秒)
- Show us who you are with a cover-letter video. (3分46秒)
- We look forward to meeting you. (3分56秒)
- I could make a little salad, turn it into a dinner for two (4分7秒)
- okay if we take a rain check? (4分7秒)
- You're not getting any younger. (4分7秒)
- the more I think about this idea, the more tremendous I think it is. (4分59秒)
- I may not be hip enough to live in Brooklyn (5分30秒)
- this could help with that (5分32秒)
- 3分~6分に登場する英語
- まとめ
作品に登場する英語を解説!
※各フレーズの登場時間は視聴手段によって異なる場合がありますので、おおよその目安としてご活用ください。
※各フレーズの日本語訳は、作品公式のものとは異なる場合があります。
3分~6分に登場する英語
I thought that was you. (3分8秒)
訳:「やっぱりあなたね。」
遠くに知り合いらしき人を見つけ、呼び止めて近づいてみたらやっぱり知り合いだった。そんな時に使える表現です。
organizational skills (3分21秒)
訳:「業務処理能力」
求人広告に書かれていた文言、なんとも訳しづらい言葉です。organization は「組織(化)、構成、団体」などの意味ですから、直訳すると「組織化する技術」でしょうか。なんだそれ?笑
あるサイトでは、organizational skills の例として次のようなものが挙げられていました。
- Administrative 「管理/経営能力」
- Creative Thinking 「創造的思考力」
- Analyzing Issues 「課題分析力」
- Project Management 「プロジェクトマネジメント」
- Group Leadership 「リーダーシップ」 など
(引用元:Top Organizational Skills Employers Value with Examples)
他にも様々書かれていましたが、要は仕事に必要なあらゆる能力のことのようです。
いや、求めすぎ笑
実際は、『求人広告の定型文』くらいに捉えておけばいいのかもしれませんね笑
a roll-up-your-sleeves attitude (3分26秒)
訳:「やる気ある姿勢」
roll-up-your-sleeves は直訳すると「腕まくり」、熟語をハイフンでつなぐことで attitude 「態度」を修飾する形容詞として用いられています。
ハイフンによる熟語の形容詞化は第1回にも登場していますので、お時間のある方はそちらもご覧ください。
Show us who you are with a cover-letter video. (3分46秒)
訳:「自己紹介ビデオでご自身をアピールしてください。」
・間接疑問文 Who you are の意味
Who you are の部分は間接疑問文と呼ばれ、「あなたが何者であるか」という名詞のかたまりを作ります。間接疑問文は名詞ですから、主語(S)や、動詞・前置詞の目的語(O)、補語(C)になります。
上のセリフでは、show O1 O2 「O1 に O2 を見せる/示す」の O2 になっています。
また、間接疑問文は、直接疑問文の語順(Who are you?)ではなく、肯定文と同じ語順であることもポイントです。
間接疑問文の例文をいくつか作ってみました。
- I don't know where he lives.
「彼がどこに住んでいるかは知らない。」 - Tell me who made you mad.
「だれがあなたを怒らせたのか教えて」
・cover letter とは?
cover letter は企業への応募書類に同封する書類で、直訳すると「送付状」ですが、ファックスにつける送付状とはまるで違い、自己のスキルや志望動機について詳しく記し、応募企業にアピールする重要な書類だそうです。
We look forward to meeting you. (3分56秒)
訳:「あなたにお会いできることを楽しみにしています。」
look forward to A は、「Aを楽しみにしている」という意味です。
ポイントとして、この to は 前置詞なので、A には名詞のほか、動名詞を用います。to 不定詞と勘違いして動詞の原形を使わないよう気をつけましょう。
〇 We look forward to meeting you.
× We look forward to meet you.
I could make a little salad, turn it into a dinner for two (4分7秒)
訳:「サラダを作るから、二人で食べない?」
・控えめな気持ちを表す could
食事への誘いの言葉で、未来の内容ですが can の過去形 could が使われています。これは仮定法過去と呼ばれる文法で、ここでは控えめな気持ちを表す
仮定法過去について、学校では主に『現在の事実と異なる内容』を表すと教わります。例えば以下の例文です。
I wish I could swim as fast as he does.
「彼と同じくらい速く泳げたらなあ。(実際は彼ほど速く泳げない)」
ところで、過去って現在から遠い時間ですよね?
仮定法にもこの『遠い』という感覚は引き継がれています。先ほど挙げた例文では、『事実から遠い』という感覚から、事実と異なる内容を表します。
また、この『遠い』感覚が気持ちの面で現れれば控えめな気持ち、すなわち『遠慮』になります。そのため、仮定法は遠慮の気持ちを表すのにも使われます。
上のセリフでは、夕食への誘い文句があまり直接的になりすぎないようにしようという、登場人物の控えめな気持ちが表れています。
・turn A into B の意味
turn A into B は、「AをBに変える」という意味です。
okay if we take a rain check? (4分7秒)
訳:「またの機会にさせてもらうよ」
rain check の本来の意味は『雨天順延券』。野球などの試合が雨で中止となった時に配られる、次戦以降の観戦に使えるチケットのことです。
また、『後日購入券(セール品が売り切れた際、再入荷時にセール価格で購入できることを証した引き換え券)』という意味もあります。
さらに、そこから派生して相手の誘いに対して、「またの機会にするよ」と別日に延期したい気持ちを表すときにも用いられます。
You're not getting any younger. (4分7秒)
訳:「もう若くないんだから」
You're not getting any younger. はよく使われるフレーズで、「もう若くないんだから」あるいは「(主に若い人に対して)いい年なんだから」という意味です。
なお、any + 比較級は否定語と共に用いて、「もうこれ以上/少しも~ない」という意味になります。
I can't wait any longer.
「もうこれ以上待てない。」
the more I think about this idea, the more tremendous I think it is. (4分59秒)
訳:「考えれば考えるほど、それはすばらしいことだと思えてきます。」
tremendous は、「(大きさや程度などが)ものすごい、とてつもない」「恐ろしい、すさまじい」という意味で、口語では「すばらしい」という意味でも使われます。
また、the + 比較級 ~, the + 比較級 … で、「~すればするほど、ますます…だ」という意味になります。
The older I get, the longer it takes to make a decision.
「年を取ればとるほど、決断に時間がかかる。」
この文法を使った慣用句もいくつかあります。
- The sooner, the better.
「早ければ早いほどいい。」 - The more, the merrier.
「(パーティーなどで)人が多ければ多いほど楽しい。」
I may not be hip enough to live in Brooklyn (5分30秒)
訳:「私は流行に疎くて野暮ったく、ブルックリンの街に似つかわしくないのかもしれない」
not be hip enough は直訳すると「十分 hip ではない、hip さが足りない」ですが、ここでの hip の意味でなんでしょうか?
実は、hip にはスラングとして、「流行に敏感な」や「格好のいい、いかした」、「物知りな」といった意味があります。
けっしてお尻が足りないわけではないんですね笑
this could help with that (5分32秒)
訳:「これ(IT企業への再就職)がそれ(時流に乗れていないという問題)に対処するのに役立つかも
しれない」
help で真っ先に思いつく意味は、help ~ 「~を助ける、手伝う」ではないでしょうか。~の部分は人や動物、グループや会社といった組織など、『手助けする相手』が入りますよね。
一方、help with ~ の意味は「~に役立つ」。~には『手助けの内容』が入ります。この表現、パッと思いつかない人が意外と多いんじゃないでしょうか? 少なくとも私はそうでした笑
ちなみに、上の二つを合わせて使うこともあります。
I'll help you with your homework.
「宿題を手伝ってあげるよ。」
・help のもう1つの重要な意味「避ける、抑える」
ここでは登場していませんが、help は can や cannot (can't) と共に用いて「避ける、抑える」といった意味になることもあります。
- I can't help it.
「(避けられない⇒)仕方がない、しょうがない、どうしようもない」 - It can't be helped.
「それはしょうがないよ。」
宇多田ヒカルの『Automatic』は、 I can't help my feel のイントロから始まって、サビにも I just can't help が登場します。
また、この意味の help は cannot help doing 「~せずにはいられない」の形でもよく用いられます。
I couldn't help laughing.
「笑わずにはいられなかった。」
まとめ
今回はここまでです。お読みいただきありがとうございました!
次回もよろしくお願いします!

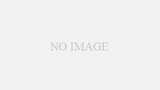
コメント