ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ主演、2015年公開の映画『マイ・インターン』に登場する英語を、複数回に分けてまるっと解説します!今回は第1回です!
- あらすじ
- 作品に登場する英語を解説!
- 作品開始~3分に登場する英語
- That's all there is. (1分13秒)
- As you can imagine, ~ (1分19秒)
- Sort of felt like I was playing hooky. (1分32秒)
- no matter where I went, as soon as I got home, the nowhere-to-be thing hit me like a ton of bricks. (1分38秒)
- come rain or shine (1分52秒)
- mind if we join you here? (1分56秒)
- You name it. (2分8秒)
- I love 'em to pieces. (2分37秒)
- Don't get me wrong (2分43秒)
- quite the contrary (2分46秒)
- Which brings me to today (2分56秒)
- when I was leaving the market (2分56秒)
- caught your flyer out of the corner of my eye (2分58秒)
- 作品開始~3分に登場する英語
- まとめ
あらすじ
華やかなファッション業界で成功し、結婚してプライベートも充実、現代女性の理想の人生を送るジュールズ。そんな彼女の部下にシニア・インターンのベンが雇われる。最初は40歳も年上のベンに何かとイラつくジュールズだが、いつしか彼の的確な助言に頼るように。彼の“豊かな人生経験”が彼女のどんな難問にもアドバイスを用意し、彼の“シンプルな生き方”はジュールズを変えていくー。そんな時、ジュールズは思わぬ危機を迎え、大きな選択を迫られることに!
作品に登場する英語を解説!
それでは、『マイ・インターン』に登場する英語で私が気になったものを解説していきます。
※各フレーズの登場時間は視聴手段によって異なる場合がありますので、おおよその目安としてご活用ください。
※各フレーズの日本語訳は、作品公式のものとは異なる場合があります。
作品開始~3分に登場する英語
That's all there is. (1分13秒)
訳:「(愛と仕事、仕事と愛、)それがすべてだ。」
心理学者、精神科医として知られるフロイトの引用です。
all there is の部分は、there is/are ~ 「~がある、いる」が先行詞allを修飾している関係代名詞節、それも接触節です。
・接触節とは?
接触節とは、「先行詞を修飾する部分が、関係代名詞のwhoやwhich、thatを挟まずそのまま続く形(先行詞と修飾部分が接触している形)」で、例えば、
① I've seen the dog which Jane was talking about yesterday.
② I've seen the dog Jane was talking about yesterday.
「私はジェーンが昨日話題にしていた犬を見かけたことがある」
という2つの文章では、先行詞のthe dogの後にJane was ~がそのまま続いている②が接触節です。
・主格の関係代名詞なのに接触節が用いられている理由
この接触節、主格の関係代名詞では通常用いられません。
おそらく、省略してしまうと先行詞と修飾部分の動詞が続いてしまい、その部分が1つの独立した文のように見え、文構造が分かりづらくなってしまうからだと思われます。
下の例文では、whoを省略するとShe likes a guy と a guy talks a lot という二つの文が重なっているように見えてしまいます。
〇 She likes a guy who talks a lot.
× She likes a guy talks a lot.
「彼女はおしゃべりな男性が好き」
ここで、there is/are ~ は、~の部分が主語とみなされるため、冒頭のall there is は厳密には主格の関係代名詞です。
しかし、allとisの間にthereが挟まることで、先行詞と動詞の連続が生じないため、接触節でも違和感がありません。
そのため、all there is は主格の関係代名詞ですが接触節となっています。
As you can imagine, ~ (1分19秒)
訳:「お察しのとおり、~」
この場合のasは「~するように」という意味で、上のフレーズは非常によく使われます。
直訳すると、「あなたが想像できるように」となるでしょうか。
似たようなフレーズとして、
- As you can see, ~ 「見てのとおり、~」
- As you can tell, ~ 「お分かりのとおり、~」
なども覚えておくと便利です!
ちなみに、この場合のtellは「話す」ではなく「分かる」という意味で、
tell A from B という形で用いると、「AとBを見分ける、区別する」という意味になります。
Sort of felt like I was playing hooky. (1分32秒)
訳:「ちょっとズル休みをしている気分になってた」
・sort of の意味
sort of は口語でよく使われるくだけた表現で、「ちょっと、まあまあ、多少」といった意味です。
似た意味を表す表現として、kind of などもあります。
・play hooky の意味
play hooky(またはhookey)は「サボる、ズル休みする」という意味のくだけた口語表現で、主にアメリカで使われているようです。
「サボる、ズル休みする」を表す表現は次のようなものもあります。
- skip class/work 「(授業/仕事を)サボる」
※風邪など正当な理由で休む場合にも使えます。 - cut school/class 「(学校/授業を)サボる」
- ditch school/class 「(学校/授業を)サボる」
※ditchは「無断で」というニュアンスが強いようです。 - slack off 「(出席、出勤しているものの)手を抜く、なまける」
no matter where I went, as soon as I got home, the nowhere-to-be thing hit me like a ton of bricks. (1分38秒)
訳:「どこへ旅しても、家に帰ったとたん、虚しさが私を押しつぶすように襲ってきた。」
・no matter where ~ の意味
no matter + 疑問詞 で、「~しようとも」という意味になります。
また、no matter + 疑問詞 という言い方は、疑問詞+ever と言うこともできます。
- no matter where ~ 「どこで/どこに~しようとも」= wherever ~
- no matter what~ 「なにを/なにが~しようとも」= whatever ~
- no matter when ~ 「いつ~しようとも」 = whenever ~
- no matter how ~ 「どんなに~しようとも」 = however ~
ちなみに、 疑問詞+ever には次のような意味もあります。
- wherever ~ 「~なところはどこでも」
- whatever ~ 「~なものはなんでも」
- whenever ~ 「~なときはいつでも」
イギリスのロックバンド、オアシス(Oasis)の名曲「Whatever」の冒頭の歌詞は次の通りです。
I'm free to be whatever I
Whatever I choose
And I'll sing the blues if I want
I'm free to say whatever I
Whatever I like
If it's wrong or right it's alright
俺は何にだってなれる
なろうと思ったものなら何にだって
その気になればブルースだって歌う
俺はなんだって言える
好きなことをなんだって
間違ってても正しくてもどっちだっていい
・as soon as ~ の意味
as soon as ~ は、「~するとすぐに」という意味です。
・nowhere-to-be の意味
疑問詞 to do で「~すべき○○」という意味になりますよね。
where to be なら、beを「いる、ある」と訳すと、「いるべき場所、あるべき場所」になります。
今回はnowhereなので、「いるべき場所がない」ということになります。
主人公ベンは仕事を退職し隠居生活。妻にも先立たれ、ひとりぼっちで時間を持て余しているため、色々なことに挑戦していますが、どれもしっくり来ていないようです。
そんな所在なさや虚無感を the nowhere-to-be thing と表現しています。
(正直、和訳が難しかったです笑)
ちなみに、nowhere と to と be がハイフン( - )で結ばれていますが、それによってnowhere-to-be が thing を修飾する一つの形容詞として扱われています。
(「10歳の男の子」と言うとき、 a ten-year-old boy というのと同じです。)
・hit ~ like a ton of bricks の意味
hit ~ like a ton of bricks は、「~に猛烈な衝撃を与える」という意味です。
a ton of ~ は「大量の~」、brick は「レンガ」のことなので、大量のレンガが上から降ってくるイメージでしょうか。
hit の部分には他にも色々な動詞が使えるようです。
- strike ~ like a ton of bricks 「~を激しく打ちのめす」
- descend on ~ like a ton of bricks 「~にものすごい勢いで襲いかかる」
- come down on ~ like a ton of bricks 「~を怒鳴りつける」
come rain or shine (1分52秒)
come rain or shine で、「晴れでも雨でも=何があっても」という意味です。
come rain or come shine や、単に rain or shine と言う場合もあるようです。
ちなみに、上の nowhere-to-be と同じくハイフンでつないで、
a rain-or-shine event 「雨天決行のイベント」のように形容詞としても用いられます。
mind if we join you here? (1分56秒)
訳:「相席していいですか。」
(Do you) mind if ~ は、「~したら気にしますか=~してもいいですか」という意味です。
また、「相席する」の意味で join が使われていますが、自分がしゃべろうと思ったらなかなか咄嗟には出てこないですよね。
(Do you) mind if ~について、注意すべきは返答の仕方。
mind は「~を気にする」という意味なので、「いいですよ」と言おうとして Yes. と答えてしまうと、文法的には「気にする(からやめてください)」という意味になってしまいます。
もし、「いいですよ」と言いたいなら、 No, go ahead. などと答えます。
ただし、他の人の体験談などを色々調べてみると、ネイティブスピーカーでない人に返答すると、Yes と No を逆の意味にとられる場合もあるようです。
そのため、次のように答えると誤解を与える可能性が低いようです。
Do you mind if 〜?ときかれた時、NoとYesは全く使わなくなった。
嫌でない時は
Sure.
Yeah! Of course.
嫌な時は、
I’m sorry. I can’t.と言うようになりました。
これで、全く誤解がなくなった。
You name it. (2分8秒)
訳:「なんでもやった」
You name it. は、「なんでも」という意味の慣用表現です。
name のここでの意味は、「(人や物)の名前を挙げる」です。同類のものを列挙した後に付け加える形で用いられることが多く、「そのほか名前を挙げられるものはなんでも」といったイメージです。
ちなみに、You name it. はあくまで慣用表現なので、返答として何かの名前を挙げる必要はありませんが、知らないと答え方が難しい表現って他にもありますよね。
個人的には、「ねえ、ちょっと聞いて」という意味で使われる Guess what. の返答の仕方を初めて聞いたとき、「そんなん分かるか!」と思いました笑(Guess what. に対する一般的な返答は What? です。)
I love 'em to pieces. (2分37秒)
訳:「彼らを心から愛してる」
to pieces は、「ばらばらに、粉々に」といった意味のほか、「完全に、とことん」といった意味があります。
また、'em は them の短縮形です。
Don't get me wrong (2分43秒)
訳:「誤解しないでほしい」
get ~ wrong は、「~を誤解する」という意味です。
文法的には、get O C の第5文型と解釈できますが、それよりも熟語として覚えておくとよいと思います。
こういう簡単な表現って、いざ言おうとするとすぐに出てこないんですよね~笑
quite the contrary (2分46秒)
訳:「むしろその逆だ」
quite the contrary は、「全く逆で、それどころか」という意味です。
contrary は「正反対(の/で)」を意味する形容詞、名詞、副詞で、quite は「まったく、すっかり」など、強調を意味する副詞です。
Which brings me to today (2分56秒)
訳:「それで、私は今日ここへ来た(=面接に応募した)」
・関係代名詞 which の非制限用法
上の文に登場する Which は「どちら」を意味する疑問詞ではなく、関係代名詞です。
関係代名詞は普通、直前の名詞(先行詞)を修飾しますよね(直前の名詞を修飾する用法を、制限用法といいます)。次の例文では、which ~ の部分は、a car を修飾しています。
① I have a car which was made 30 years ago.
「私は30年前に造られた車を1台所有している。」
一方、先行詞と関係代名詞の間に「,」が入った例文②の用法を非制限用法といって、文の意味が変わります。
② I have a car, which was made 30 years ago.
「私は車を1台所有しているが、それは30年前に造られたものだ。」
例文①と②で何が違うかというと、例文①では「所有している車のうち、30年前に造られたものは1台」と言っているだけなので、他にも車(新車や10年前の車など)を所有している可能性があります。
一方、例文②は始めに「所有している車は1台」と言った後、「それは30年前のものだ」という情報を追加しています。そのため、所有している車は1台のみです。
このように、制限用法は先行詞のみを対象とした追加情報を表すのに対し、非制限用法は前の文全体に対する追加情報を表します。
言い換えると、非制限用法では、先行詞まで(コンマの前まで)とその後ろの部分は別の文と言えます。
この非制限用法ですが、先行詞としてピリオドで区切られた前の文を指すこともできます。上のセリフを少し前から引用します。
I just know there's a hole in my life, and I need to fill it. Soon.
Which brings me to today, ~(略)~
「私は自分の人生にぽっかり穴が開いていることに気づき、それをすぐに埋める必要があった。
それで、私は今日ここへ来た(=面接に応募した)」
Which は動詞 bring の主語であり、面接に応募した動機を意味しますが、その内容は前の文で語られています。
・bring A to B の意味
bring A to B は、「A(モノ、人など)をB(人、場所など)に持ってくる、連れてくる」という意味です。
これと似た表現に、take A to B 「AをBに持っていく、連れていく」があります。私は、メジャーリーグの球場で流れる『Take me out to the ballgame(私を野球に連れてって)』で覚えました。
なお、bring は相手のいる場所に持っていくイメージ、take はどこか別の場所に持っていくイメージです。
when I was leaving the market (2分56秒)
訳:「店を出ようとしたとき」
動詞 leave には沢山の意味がありますが、場所を表す単語と共に使う場合の使い方を整理します。
leave は「今いる場所(現在地)」と「これから行く場所(目的地)」のどちらとも一緒に使いますが、使い方が異なります。
- leave + 現在地 「~を去る、離れる」
(例)I'm leaving Tokyo soon.
「もうすぐ東京を発つ。」 - leave for + 目的地 「~に向かう」
(例)I'm leaving for Tokyo soon.
「もうすぐ東京に向けて出発する。」
また、現在地と目的地両方を一つの文に含めることもできます。
I'm leaving Tokyo for Osaka soon.
「大阪に向けて、もうすぐ東京を発つ。」
caught your flyer out of the corner of my eye (2分58秒)
訳:「あなたたちの張り紙が目に留まった」
out of the corner of one's eye は、「横目で、こっそりと(見る)」という意味です。
catch のほか、glimpse(ちらっと見る)や see、look at などの動詞と共に用いられます。
ちなみに、catch と eye を使った catch one's eye(s) 「~の目に留まる、~に目が釘付けになる」という表現もあります。
Her smile caught my eye(s).
「彼女の笑顔に私は目を奪われた。」
まとめ
いかがだったでしょうか。作品開始からわずか3分(オープニングロゴを除けば約2分)ですが、勉強になる表現が沢山ありました!
このペースで解説を続けると作品の終わりまで無事たどり着けるかかなり不安ですが(笑)、気長にお付き合いいただけたらうれしいです!
次回もよろしくお願いします!

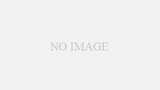
コメント